平成28年熊本地震の影響により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

◎「小規模保育総合補償制度」の被害(事故)のご連絡、お問い合わせ
当協議会の「小規模保育総合補償制度」にご加入いただいております会員の方からの被害(事故)のご連絡、お問い合わせは、以下の連絡先にて承っておりますので、ご案内申し上げます。
【小規模保育総合補償制度・事故連絡先】
≪施設管理者賠償補償≫
三井住友海上火災保険株式会社
火災新種損害サポート部 第1保険金お支払センター
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1 電話:03-3259-6727 FAX:03-3259-7198
≪保育園児向け傷害保険≫
三井住友海上火災保険株式会社
傷害疾病損害サポート部 傷害疾病第3保険金お支払センター
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1 電話:03-3259-8107 FAX:03-3219-2927
被害(事故)のご連絡については、「小規模保育総合補償制度のご案内(H28年度加入用)」(PDF)のパンフレットの17ページに「事故報告書」の書式がございます。
こちらの書式の用意が難しいときも、上のお問い合わせにどうぞご連絡ください。

よろしくお願い申し上げます。
「3歳の壁」を打破する小規模保育の3~5歳児の受け入れ拡大を待機児童緊急対策に盛り込んでください!
2016年3月25日
「保育園落ちた」のブログに端を発し、3月25日、待機児童解消に向けて政府・与党が検討している緊急対策の原案が判明しました。
毎日新聞 待機児童対策 一時預かりで臨時対応・・・政府原案
http://mainichi.jp/articles/20160325/k00/00m/010/158000c
一時保育預かりの臨時対応や待機児童が特に多い0~2歳時対象の小規模保育所の受け入れ拡大などが盛り込まれています。
保育所の受け入れ人数を増やす対応は、面積基準や人員配置基準を 従来のものを下回るのでなければ、評価できる取り組みです。

待機児童緊急対策では、0~2歳児対象の小規模保育所の受け入れを拡大する方向です。
けれど、小規模保育所で本当の問題は、日本経済新聞などのメディアでも取り上げられている 「3歳の壁」といわれる小規模保育所を卒園した3歳児の受け入れ先です!
「3歳の壁」は当協議会で実施した小規模保育経営実態調査でも、50%もの事業者が「3歳以降の受け皿としての連携施設が見つからない」という課題をあげています。
小規模保育所は、保育の受け入れを2歳児までと制限されているため、 その可能性を活かしきれていません。 全国小規模保育協議会からは、小規模保育所で、3歳~5歳も受け入れられるように制度改正を求めます!
小規模保育白書2016年版発売されます!
2016年3月25日

みなさま、こんにちは!
昨年4月より多様な保育ニーズに応えようと始まった子ども子育て支援新制度。
この制度で小規模保育も認可として位置づけられるようになりました。
これに伴い一気に1655もの施設が開園されましたが、もともと小規模保育所は以前より各地で志ある事業者に運営されていました。
そうした黎明期からの歩みや大規模園とは違う特長、法制度上の課題など、制度発足前のタイミングで切り取った小規模保育の断面を写した「小規模保育白書」(第一弾)が昨年、発刊されました。
そしてこのたび、制度施行後の現状や明らかになってきた課題を伝える「小規模保育白書(2016年版)」が発刊されます。(3月31日予定)
利用者、保育者の声、施設運営者インタビュー等のコラム類、開園ルポが現場のリアルを伝え、ページ数も35%増と大幅にアップ、読み応えある内容になっております。
みなさま、ぜひお手にとってご一読下さい!
小規模認可保育所、経営実態調査アンケート回答結果詳細
2016年2月22日
2015年4月、「子ども・子育て支援新制度」が始まり、全国で1,655園もの小規模認可保育所がオープンしました。
小規模認可保育所ですが、都市部では待機児童問題解決の切り札として、地方では人口減少時代の保育制度維持のための解決策として大きく注目を浴びています。
従来の認可保育園に比較し人員配置が手厚いことからコミュニケーションが密であり、保護者は信頼してお子さんを預け、子どもは日中安心して過ごすことができる小規模保育、今後も広く普及してほしいところです。
今回、当協議会では新制度発足後に小規模認可保育所が運営にあたりどんな課題を抱えているか、という調査を行い全国102事業者、148園より回答をいただきました。
施設運営者からどんな課題が挙げられたのか、国や自治体は何をすべきか・・・
詳細はこちらのファイルをご覧下さい。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
小規模保育専用団体保険、本日2/10より受付開始!
小規模認可保育所向けの団体保険が昨年4月にスタートして丸一年を迎えようとしています。
おかげ様で多くの施設にご利用いただき、来年度の加入に関するお問い合わせが増えています。
一方、昨年4月2日にご案内したとおり、公的保険の適用についても政策提言を行った結果、晴れて小規模認可保育所が(合せて地域型保育のうち、居宅訪問型以外の保育類型も)公的保険である日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となりました!

※日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
小規模認可保育所は災害共済給付制度の加入対象になりました。
内容等詳細についてはこちらをご確認ください。
補償内容、ご加入手続き詳細についてご不明な点がございましたら日本スポーツ振興センターにお問い合わせください。
(補償内容の説明や加入手続きなどは、当協議会では行っておりませんのでご了承ください)
小規模保育向け団体保険、平成28年度新規受付、2月に開始予定!
2015年12月25日
みなさま、こんにちは!
小規模認可保育所向けの団体保険が4月にスタートして早8ヶ月が過ぎました。
おかげ様で多くの施設にご利用いただき、来年度の加入に関するお問い合わせが増えています。
そこで、平成28年度の保険(2016年4月1日-2017年4月1日)の加入手続きについてお知らせします。
また、当協議会の政策提言などにより、今年度から、小規模認可保育所も
「災害共済給付制度」(独立行政法人日本スポーツ振興センター)に加入が可能となっております。
当協議会の団体保険と合わせますとより手厚い補償となります。
「災害共済給付制度」(独立行政法人日本スポーツ振興センター)の詳細については、こちらをご覧ください。
小規模保育向け専用団体保険
正式名称:小規模保育総合補償制度
毎年4月1日スタート、翌年4月1日まで一年ごとの保険
現在、平成28年度版のパンフレットを作成中です。
パンフレットが出来上がり次第公開いたします。
補償内容には、若干変更がある予定です。
今年度の平成27年度団体保険(小規模保育総合補償制度)の詳細やパンフレットは、こちらを参考にしてください。
■現在会員外で平成28年度(2016年4月)より新規加入をご希望の団体様
・保険加入手続きの前に必須の会員登録(当協議会ご入会)を1月4日より受付
※平成27年度の年会費はお支払い不要です。
・団体保険の手続きを2月1日頃より開始予定(2016年4月分スタート分)
※保険加入手続きは、当協議会に正会員ご登録、年会費(平成28年度)のお支払、口座振替手続き完了後に開始します。
(正会員入会のお手続きに約1週間必要です)
※当協議会の正会員である小規模認可保育所が加入対象となります。
※認可外の小規模保育施設、事業所内保育所は対象外となりますことをご了承下さい。
■現在正会員で今年度保険加入し来年度も加入をご希望の団体様
・団体保険の手続きを2月1日頃より開始予定(2016年4月分スタート分)
※入会手続きは不要です。

【掲載情報】読売新聞11月17日「住まい再考 ~高齢者住宅や保育所に活用~」に幹事団体フローレンスの事例が紹介!
2015年11月18日
去る11月17日、読売新聞夕刊の特集記事「住まい再考」にフローレンス「おうち保育園」事業部の取り組みが紹介されました。
少子高齢化に伴う空き家の増加、共働き世帯増加による子どもの預け先不足といった社会問題を解決の一事例として、空き家を活用した事例が紹介されたのです。
当協議会としては、保育所運営の高い志があり、その後開園実務の過程で空き家が物件候補の一つとしてあげられる、という前提で取材対応をしましたが、記事のテーマが「住まい再考」のため家屋活用としての保育所運営(や高齢者住宅)という切り口になっています。
保育所運営をめぐって世の中の様々な受け止め方を示す一例としてご高覧下さい。
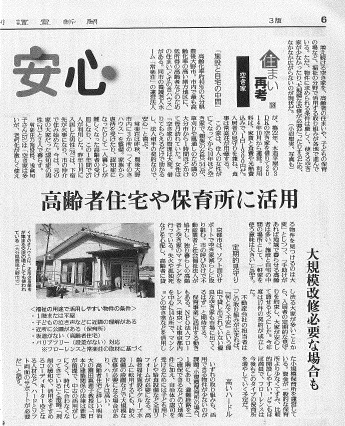
記事のダウンロードはコチラ
【報告】小規模保育のバイブル「小規模保育白書」[Kindle版]が発売になりました!
2015年9月28日
単行本で刊行された「小規模保育白書」の電子書籍[Kindle版]が発売になりました!
小規模保育のこれまでの歩みと新制度における全容を知りたいという声にお応えするかたちで刊行された「小規模保育白書」。
Kindle版は、単行本よりご購入いただきやすい価格になっております。
この機会に、是非、ご覧ください!
amazon.co.jpで単行本、Kindle版のどちらも発売中です!
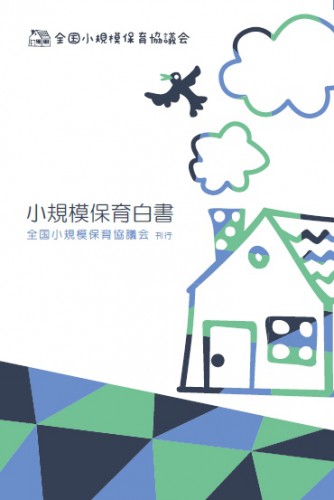
小規模保育白書
「聞こう!語ろう!現場の本音」~9/5(土)保育研修会を開催します~
2015年8月19日
全国小規模保育協議会が主催する保育研修会。
次回の研修会の詳細が決まりました!!

【日時】9月5日(土)13:45~17:00(受付13:15~)
【場所】NPO 法人フローレンス オフィス
(東京都千代田区飯田橋 3-3-7 秋穂セントラルビル 2F)
アクセス http://www.florence.or.jp/about/access/
*地下鉄・JR 飯田橋駅より徒歩約2~5分
【参加費】
■会員 1,000 円
■会員外 3,000 円
※参加費は受付にて集めさせていただきます。
【定員】70 名(事前申し込み)
【スケジュール】
■全体会(13:45~14:55)
13:45~ 国の動向について
~理事長 駒崎~
14:00~14:55 基調講演
『小規模保育の特性とその保育について』
~土谷みち子先生(関東学院教育学部 こども発達学科教授)~
■分科会(15:00~16:25)
テーマ ・親支援・保護者対応
・運営の工夫あれこれ
・異年齢保育の環境と工夫
・他の園ではどうしてる?
(例:給食のこと、配慮が必要な子どものこと・・・etc)
※テーマはリクエストにより、変更になる場合もございます。
■全体会(16:25~16:55)
~各分科会からの報告~
■閉会(16:55~17:00)
~理事長 駒崎より~
複数でのご参加も大歓迎です。
講演会と分科会で現場のみなさんがより学びを深めていただける会となることを願っております。
多くの皆様方のご参加をお待ちしております。
【9/5(土)保育研修会】申込みフォーム
ご質問、ご不明な点がございましたら、下記へお問合せください。
問合せ先 : 全国小規模保育協議会
Mail:jimukyoku@syokibohoiku.or.jp
